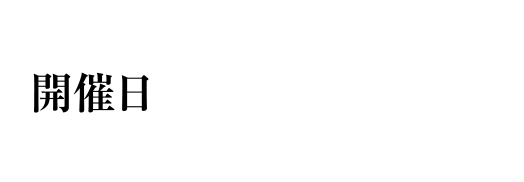

富山県高岡市伏木地区で、毎年5月の第三土曜日とその前日に行われる「伏木神社春季例大祭」、通称、「けんか山」。
昼は美しい花傘を広げた7基の花山車が町を巡り、夜には提灯を灯した曳山同士の激突「かっちゃ」が行われます。
町を離れた若者もこの日のために帰り、汗と声と力で祭りに命を吹き込む。
その姿には、地域への誇りと未来への願いが宿ります。
2024年1月1日に発生した能登半島地震。伏木もまた、大きな被害を受けました。
爪痕は今も残りますが、それでも私たちは立ち止まりません。
祈りと誇りを、次の世代へ繋ぐために。
今年も「けんか山」は行われます。
規模は縮小し、地域外からの観覧はご遠慮いただきますが、曳山は伏木の復興の灯を絶やさぬように、力強く進みます。
曳山が進む限り、私たちの魂は前を向き続けるのです。

「知る」祭りの起源と由来
かつて越中国の国府が置かれ、北前船の寄港地として栄えた伏木。
古くから海とともに歩んできたこの港町では、海の恵みに感謝し、航海の安全を願う祭礼が受け継がれてきました。
祭りの始まりは、江戸後期の文政3年(1820年)。
中町が最初の曳山「ひょうたんやま」を創設したのを皮切りに、町の発展に伴い明治期までに山車が次々と加わり、祭りの姿が形づくられていきました。

この祭りは、伏木神社の春の例大祭にあわせて行われる神事でもあり、200年以上にわたり地域の人々によって受け継がれてきました。曳山を一年かけて整え、磨き、曳く。技と誇りを次へと紡いでいきます。
けんか山は、伏木の歴史、暮らし、人々の絆が凝縮された、地域の魂そのものなのです。

「魅せる」昼と夜、ふたつの顔
昼と夜で姿を変える曳山には、伏木の人々が代々繋いできた想いが、いまも確かに息づいています。
「花山車」の巡行では、彫刻や装飾が施された華やかな山車が町を練り歩き、色とりどりの花模様や職人の技巧が目を楽しませてくれます。各町が祀る福神を中心に、職人たちの技と信仰が融合したその姿は、まさに“動く美術品”。
高さ約8メートルの山車は、各山町の人々が1年をかけて手入れを重ね、丹精込めて受け継いでいるものです。それぞれの山車には町の象徴である「だし」=「鉾留(ほこどめ)」が掲げられ、ご神体や人形が鎮座しています。

伏木曳山祭「けんか山」の最大の見どころは、曳山同士が激しくぶつかり合う、夜のクライマックス「かっちゃ」です。
「かっちゃ」とは、「かちあう(ぶつかり合う)」を語源とし、山車が正面からぶつかる様子はまさに「けんか山」の名にふさわしい迫力。勝敗こそつかないものの、町の誇りを懸けた勝負は、見る者の心を揺さぶります。
重さ8トンの山車が約360個の提灯をまとって闇夜を進み、太鼓の響きと若衆の「イヤサー、イヤサー」の掛け声が祭りを最高潮に導きます。この掛け声には「弥栄(いやさか)=ますますの繁栄」を願う意味が込められており、地域の発展幸せを祈る響きでもあります。
ぶつかり合ったあとは、互いの健闘を称えて総代同士が握手を交わし、若衆の町内賛歌で「かっちゃ」は幕を閉じます。

「訪れる」アクセス&周辺観光
伏木駅はJR氷見線で高岡駅から約20分、駅から会場までも徒歩圏内とアクセス良好。
周辺には歴史や自然を感じられるスポットが点在しています。
なかでも注目は、2022年に国宝に指定された「勝興寺」。荘厳な建築美は圧巻で、けんか山とともに伏木の歴史にふれるひとときを楽しめます。
また、伏木は万葉集の歌人・大伴家持ゆかりの地としても知られ、「高岡市万葉歴史館」では、万葉の世界や伏木に息づく文化に触れることができます。
晴れた日には「雨晴(あまはらし)海岸」へ。
海越しに立山連峰を望む絶景は、まさに富山を代表する風景です。
本年も「けんか山」は来場者を制限しての開催となりますが、伏木の町は変わらず皆さまを歓迎しています。
| 5月17日(土) <昼の部> |
5月17日(土) <夜の部> |
|---|---|
| 10時00分 出発式 10時20分 曳出 〜 14時30分 終了 |
17時00分 曳出〜24時00分 終了 |
伏木地域外からのご来場はご遠慮願ます。
駐車場はありませんので路上駐車はしないでください。
<ライトアップ> 5月16日(金)19時~21時
山倉前(予定)にて、花山車のライトアップとともに、威勢のいい囃子で祭の前夜を盛り上げます。
<神輿渡御(みこしとぎょ)>5月16日(金)9時〜17時
伏木神社の春季例大祭の神輿の巡行に、子供たちの母衣武者行列や、花傘、太鼓が随徒します。
→ 令和7年度伏木神社春季祭礼曳山順路
●今年の伏木曳山祭は、能登半島地震の影響により、伏木地域外からの誘客は行わず、地域住民の活力を創出するお祭りとして実施します。
●曳山順路は、震災の影響により内容が予告なく変更になる場合があります。
日頃から伏木曳山祭実行委員会にご理解とご尽力を賜り、厚くお礼申し上げます。
去る2024年1月1日に石川県能登半島を中心に「令和6年能登半島地震」が発生し、伏木地区も液状化により道路は陥没し、建物や電柱が傾くなど大きな被害を受けました。行政、企業、地域住民が団結し、少しずつではありますが、復興に向けて動きだそうとしています。
そこで、伏木といえば、「けんか山祭り」、この地域が一年で一番熱くなるお祭りです。一部インフラも整わないなかではありますが、お祭りを通じて地域住民に元気を届けることが出来るのではないかと考えます。
可能であれば、 安全を確保し、可能な範囲でお祭りを実施し、地域を盛り上げていければと考えております。
つきましては、 趣旨にご賛同をいただきサポーター役として、祭のPRや祭のノウハウの提供、資金の提供を仰ぎたく何卒ご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
<振り込み口座番号>
金融機関名 高岡市農業協同組合 伏木支店
口座名義 伏木曳山祭実行委員会
口座番号 6026290
預金種目 普通貯金